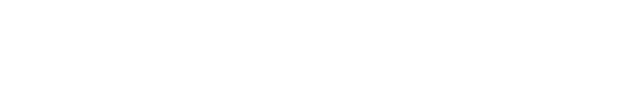補中益気湯
戦乱の世に生まれた補中益気湯
補中益気湯(ほちゅうえっきとう)は、13世紀の中国・金王朝の時代に登場した方剤です。日本では鎌倉時代に相当する時期で、当時の金は北方のモンゴル勢力に圧迫されつつありました。開封(現在の河南省)では、戦乱とともに謎の熱病が発生したと伝えられます。
従来の麻黄湯などで対応しても、多くの兵士が回復せずに命を落としました。この状況に対して、金代の医師・李東垣(りとうえん)は発想を転換し、麻黄湯のような攻撃的な方剤だけではなく、体力低下を補う発想が必要だと考えました。李東垣が本当に開封に滞在していたかどうかは明らかではありませんが、当時の惨状に触発されてこの処方を創案したと伝えられています。
人参と黄耆のコンビネーションの誕生
補中益気湯の骨格は、人参(にんじん)と黄耆(おうぎ)。滋養強壮に用いられる人参に加え、黄耆は汗によって気が漏れ出るのを防ぐ働きがあるとされ、体表を引き締め、バリア機能を高めると考えられてきました。この2つを合わせることで、疲労・倦怠感・虚弱体質などに対する高い効果が得られると考えられています。
この人参+黄耆の組み合わせを主軸とした処方群は、参耆剤(じんぎざい)と呼ばれ、補中益気湯のほかにも数種類存在します。韓国料理の参鶏湯(サムゲタン)も、広い意味で参耆剤の発想に通じています。
補中益気湯は、消化機能を整えながら、体力・免疫を回復させる目的で用いられます。とくに「病気ではないけれど、疲れやすく、風邪をひきやすく、なかなか回復しない」といった慢性的な体調不良には向いています。また、現代においてはインフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの回復期や、感染予防の文脈でも使われることがあります。
補中益気湯が効果的な場面
気虚による以下のような症状に対して、とくに効果が期待されます:
-
疲れやすく、気力が出ない
-
食欲が落ち、痩せやすい
-
昼食後に眠くなる
-
風邪をひきやすく、長引きやすい
一方で、体力が著しく低下している場合や、強い炎症や高熱をともなう急性期には適応しないこともあります。体質やタイミングを見極めて使用することが重要です。
現代人にも応用可能なこの処方──補中益気湯──は、単なる古典薬方ではなく、疲弊した現代社会へのメッセージを秘めていると言えるでしょう。

チョウセンニンジン(株式会社ツムラ提供)

キバナオウギの畑(写真提供:株式会社ツムラ)