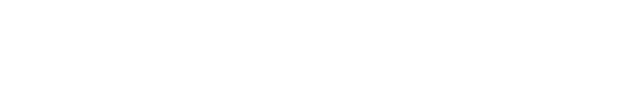当院は漢方をこのように使っています
こんな症状、ありませんか?
・風邪をひいたあと、咳だけがなかなか取れない。
・昼食をとると急に眠くなって、仕事にならない。
・月経前になると、イライラや頭痛、めまいがひどい。
・冷え性で、靴下を重ね履きしても足が氷のように冷たい。
・肩こりや頭痛が慢性的で、痛み止めが効かない。
・動悸やほてり、発汗といった更年期のつらさ。
・検査では異常なし。でも、めまいやふらつきが続いている。
こういった症状に心当たりのある方は、けっこういらっしゃるのではないでしょうか。
現代医学の検査では「異常なし」と言われる。でも、つらさは確かにある。その違和感を、医師も患者さんも少しずつ感じはじめています。私も日々の診療のなかで、そうした「説明しきれない体調不良」に直面することが多くなりました。
では、どうしたらいいのでしょうか?
もちろん、必要な検査はしっかりと行います。重大な病気が隠れていないかを確認することは、西洋医学の大切な役割です。ただ、検査で何も出なかったあと、まだ続く体の不調に対して、「じゃあ気のせいです」で済ませていいとは思いません。
そんなとき、私がもう一つの選択肢として大切にしているのが「漢方」です。
漢方:1800年前から続く「もうひとつの医学」
漢方医学は、いまから1800年前、中国で張仲景という医師が著した『傷寒論』に端を発します。その後、日本にも伝わり、日本独自の進化を遂げてきました。江戸時代には、徳川家康が自ら生薬を煎じて飲んでいたほど、漢方は医療の中心にありました。実はその頃、麻酔薬として漢方を使い、世界で初めて全身麻酔の乳がん手術を行った医師もいます。また、天然痘や梅毒などの感染症に対しても、漢方で立ち向かっていました。かなりの効果を上げていたといわれています。
ちなみに、「漢方」という言葉自体は、江戸時代にオランダから入ってきた「蘭方(らんぽう)」=西洋医学と区別するために生まれた名称です。
江戸の昔には抗生物質も採血もCTもありません。でも、当時の漢方医たちは、地域で手に入る生薬を使って、目の前の患者をなんとか治そうとしました。感染症や慢性病にも立ち向かっていました。今のように科学的な検査はありませんでしたが、その分身体所見は丁寧に記述されています。その姿勢には、今の医療人にも学ぶことがあると思っています。
現代医学と漢方医学は「別物」ではありません
漢方ってなんだか昔のもの、という印象をお持ちの方もいるかもしれません。でも実は、今の医療のなかにも漢方由来の知恵が数多く生きています。
たとえば、便秘薬として使われるセンノシド。これは漢方でいう「大黄」から成分を取り出してつくった薬です。血糖を下げる薬の中には、植物由来の成分から開発されたものもありますし、強心薬のジギタリスももともとは植物から取られたものです。
つまり、漢方と西洋医学は対立するものではなく、むしろひとつの連続線上にあると私は考えています。
「漢方って、飲んでみないとわからない」と言う理由
漢方薬は、ツムラやクラシエなどのメーカーがアルミパックのエキス剤として製造するようになって以来、安定した品質で使えるようになりました。いまは保険適用にもなっており、ひと月1000円前後の負担で継続できる方も多いです。
私自身、西洋医学の専門医ですが、患者さんの状況によっては漢方薬を積極的に提案しています。
もちろん、漢方が苦手な方に無理強いはしません。「よかったら、漢方でご相談に乗れることがあるかもしれません」とお声がけしています。
不思議なことに、「飲んでみたら効いた」という方が、気づいたら漢方ファンになっていることが多いのです。そして、「自分に合う漢方薬を教えてほしい」というご相談も少なくありません。
まとめ:あなたに合う治療法を一緒に考えます
くすき内科クリニックでは、西洋医学と漢方医学の両方の視点をもって診療しています。
症状が続いているけれど、どこに相談したらいいか分からない、そんなときはぜひ一度お話を聞かせてください。
あなたの体に合った「治し方」を、一緒に探していきましょう。